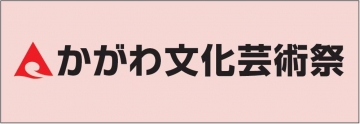「東京物語」はなぜ名作なのか?映画監督が案内する小津安二郎の世界

令和7年11月23日(日)。善通寺市にあるZENキューブで、さぬき映画祭恒例企画「映画ゼミナール」が開催されました!今回は、香川県で活躍される梅木監督と香西監督のお二人を迎え、名匠小津安二郎監督の『東京物語』のコメンタリー上映が行われました。
映画を観ながら監督たちの解説や制作の裏話を聞ける、とても贅沢な時間。その様子をご紹介します。
二人の映画制作の始まりと、出会い

まずは監督お二人の「映画との出会い」の話からスタートとなりました。
梅木監督は、大学院で修士論文執筆中に、同級生からさぬき映画祭の映像塾「映画制作実践講座」を勧められたことがきっかけで、映画制作の道に進みました。その方は偶然にも香西監督の高校時代の同級生で、これが二人の出会いになりました。その後、脚本の面白さに惹かれ、同映像塾「シナリオ講座」に進み本格的に映画制作に携わることに。
一方、香西監督は、幼少期から物語を作ることが好きで、新聞記者を志すも叶わず銀行にて社内報を担当し、文章で伝える楽しさに触れます。転機になったのは、脚本家・内館牧子さんの講演会。三菱重工で13年間、社内報を担当していたと聞き、自身も同じ境遇だったことで脚本家を目指そうと思い立ちました。
その後、東京芸術大学 大学院 映像研究科を受験するため、シナリオ講座を受けたいとさぬき映画祭事務局に相談したことからシナリオの勉強をスタート。
大学院には落ちたものの、シナリオ講座の講師を務めていた中島貞夫監督から「学校に行かなくてもいい、とにかく映画を撮りなさい」と背中を押されたことが本格的に映画制作をはじまるきっかけとなったのだそう。
お二人とも、さぬき映画祭の講座がきっかけとなり、映画づくりの道が大きく開けていったというのが、とても印象的でした。
上映前の「見どころポイント」

日本だけでなく世界で高い評価を得ている「東京物語」ですが、上映前に注目してほしいポイントを聞かれた両監督。
何度もこの作品を観てきた梅木監督は、あらためて心を動かされたシーンがあるそうで。
「お母さんが夜しくしく泣くんですよね。なんだかジーンときてしまって。」と、今まで観たときには何も引っかからなかった場面が、年齢を重ねた今、胸の奥にすっと入り込んできたのだといいます。
「子どもたちはそれぞれ順調に育って立派になって巣立っているのに、気づけば自分だけが置いてきぼりにされたような感覚」母親の気持ちが、自分自身の人生ともどこか重なって見え、思わずぐっときてしまったーーと感慨深く語る梅木監督。
映画は観る側の年齢や経験によって、その表現をまったく変えて見せるもの。同じ作品でも“人生のどの地点で再会するか”によって、新しい扉がそっと開くのだということを改めて感じさせてくれるエピソードでした。
今回の上映が決まったことをきっかけに、初めて『東京物語』を鑑賞したという香西監督。そこから小津監督について徹底的に調べ、作品に向き合ってこのコメンタリー上映に臨まれたといいます。
特に心を動かされたのは、小津安二郎の“独自の美学”。俳優が現場に入る前に、ヤカンや箪笥、ちゃぶ台といった小物の配置をセンチ単位で調整し、ときには家一軒丸ごと引っ越してきたかのように自宅から持ってきて、撮影所に再現する徹底ぶり。
カメラマンは「RECボタンを押すだけ」と言われるほど、フレームの中に完璧な世界を作り上げる。その静謐な画面は偶然ではなく、緻密な設計のうえに成り立っていたのだと語ります。
また、劇中に登場する看板文字の多くは、小津監督自身が筆をとったもの。画面の細部にまで行き届いた美意識に、会場からは感嘆の声が上がりました。
司会の帰来さんからは「昭和28年が舞台の映画ですが、脚本が4月に書き上がり、7月に撮影、10月に公開されるというスピード感に驚いた」とのこと。日本映画の全盛期ということもあり、それくらい小津監督に力があったということが伺えます。そして、終戦からわずか8年という時期に、この作品が世に出たことにも、改めて深い意味を感じそうです。
さらに興味深いのは、年老いた父親役の笠智衆さんが当時49歳で、長女役の杉村春子さんとはたった2歳しか違わなかったという事実。笠さんは背中に座布団を入れて身体の丸みを作り、70代の父親の佇まいを作り上げていたのだそう。画面の静けさの裏に、そんな努力が隠れていたんですね。
小津映画に流れる“日常の中の悲劇”

物語の序盤、東京を訪れた老夫婦は、子どもたちから温かく迎えられます。しかし日々の生活に追われる息子や娘たちは、次第に両親への対応が後回しになっていきます。
「邪険にするのに引き止める、追い出したことにはしたくないんでしょうね」と香西監督。観ている側は、そんな老夫婦のさみしさに胸がきゅっと締めつけられますが、同時に、自分も同じ立場ならこうなるかもしれないと子どもたちの気持ちも理解できてしまう。そのリアルさが、静かな痛みを残します。
そして、子どもたちに迷惑をかけまいと、知り合いの所へ身を寄せるシーンでは、
梅木監督は「子どもが出世しているのに、親が宿なしって切ないですよね…」と語り、
帰来さんも「このシーン、好きなんですよ」としみじみ続けます。
物語はいよいよクライマックスへ。
尾道へ戻った矢先、老妻・とみが倒れ危篤の知らせが届きます。
ここで梅木監督が指摘したのは、冒頭にも登場したお寺やお地蔵さんの“距離感”の変化。
「最初のシーンに出ていたお寺やお地蔵さんが、より近くなっていて、だんだん死期が近づいていることを表す隠れた演出ですね」と語り、何気ない風景の中に潜む小津監督の繊細な仕掛けを教えてくれました。あさらに香西監督が注目したのは、蚊取り線香のシーン。
「蚊取り線香は、凄いこだわった演出されてるんです」と、線香の燃え具合で時間の流れを表現する細やかな演出について解説。セリフに頼らず、静かな“気配”だけで物語を進める小津作品ならではの魅力が、より深く伝わってきました。
その後、とみは静かに息を引き取ります。
ここでも小津監督らしい“見せない演出”が際立ちます。
香西監督「“死”そのものを映さないんですよ。これが海外の監督たちから高く評価されているポイントで。外国映画だと、もっとドラマティックに死を描くことが多いんです。」
そしてこの作品で、名台詞と言われている、紀子が息子の敬三の到着を老父・周吉に知らせに来るシーンでは
「綺麗な夜明けだった。…あぁ…今日も暑うなるぞ。」という周吉のセリフに、
「昨日と同じように日が沈み、そしてまた昇る。その何気ない日常の延長線上に死があることに意味がある」のだと、香西監督は語ります。
小津監督が描く、日本的で静かな死生観が沁みるシーンです。
70年以上も愛される作品「東京物語」の魅力

『東京物語』が公開されてから、すでに70年以上。
それでも色あせず、多くの映画ファンの心を掴み続けるのはなぜなのでしょうか?
帰来さんは、老父・周吉の最後のシーンの台詞に触れながら、「老父・周吉が紀子に『実の息子・娘は冷たかったけど、他人のあんたは優しかった』って言ってたけど、それほど実の息子や娘が悪いとは思わないんですけどね。良くした方だと思うんですよね。70年前と今とでは家庭の価値観とか違うんですかね。あの当時だと、子どもは親に尽くすものだとか奥さんは旦那に従うものだという時代だからでしょうかね?」と当時の価値観への疑問を投げかけると、香西監督からは「コミュニケーションが取れていなかったんでしょうね。お子さんが生まれた時に報告があったくらいで、滅多に会ってないから、子どもの時の記憶と邪険にされたのだ余計腹が立ったのかもしれないですね。この作品は観る年代によって感じ方が違うと言われていて、私も昔チラッとみた時は何も思わなかったんですけど、今改めて観るとお父さんとお母さんの気持ちも分かるし、(長女の)シゲさんがそんなに嫌な人に映らなかったんですよね。若い人が見たら意地悪に見えて京子さんの気持ちに共感することが多いと思うんです。何回観てもいい映画だなと思いました。」
さらに香西監督は、小津作品が世界中の映画監督から愛される理由にも触れます。
「いろんな監督に絶賛されているんですけど、カメラが動かないのは、動かないものよりも、動くもの・人や感情を際立たせる効果があると言われていて、小津監督の大ファンを公言しているヴィム・ヴェンダース監督は『小津のカメラは世界で最も動かない。でも、彼の映画ほど人生が動いている作品はない』と語っていて、マーティン・スコセッシ監督も『小津の静止したカメラは、心の中の時間を撮っている』と、世界の巨匠たちがカメラが動かないことで動かす逆説的なことを評価しているんです。」と小津監督作品の特徴である低い位置に固定され、ほとんど動かない撮影手法の魅力について教えてくれました。

梅木監督からは「家族を持つと、親より自分の仕事や子供達との生活に追われるものも分かりますよね。私の母が亡くなった時、映画祭時期でバタバタしていたので寂しさを紛らわすことができてよかったと改めて思いました。母が着物を好きで、今日着てきた着物も母の着物。私もこの着物が似合う年になったなと思いながら着てきました。」と
母から受け継いだ着物をまといながら語るその姿は、『東京物語』が描く世代間のすれ違いや、親を思う気持ちの複雑さそのもの。
生きてきた時間の分だけ、この映画が胸に触れる場所も変わっていくーー
そんなことを実感させる素敵なエピソードでした。
未来の監督たちへーお二人からのメッセージ

トークの終盤、梅木監督は、海外の映画祭で投げかけられた思い出深い言葉を紹介してくれました。
「小津安二郎や黒澤明のように、100年以上世界中の人から愛される映画を作る監督の国の映画監督なのだから、あなたも100年残る映画を作りなさい」
そんな励ましを、さまざまな国の映画関係者から受けたと言います。
「古い映画ですけど、家族のあり方や人の心の普遍性がしっかり刻まれています。流行を追いかけるのもいいですけど、本来の日本の良さを考えながら作品を作りたいなと思います。」と力強く語ってくれました。
続いて香西監督も、これから映画を目指す若い世代へ向けてエールを。
「撮影方法や演出を学ぶ上でも、『東京物語』は一度観ておくべき一本です。小津監督の手法を知った上で、自分の撮り方に活かすのがいいかなと思います。世界の映画監督たちも影響を受けている作品ですからね。」
日本映画の原点に触れながら、自分の方法を模索してほしいーー
そんな深い願いを込めて、上映会を締めくくってくれました。


趣味の消しゴムはんこで、小津監督とヒロインの原節子さんを表現してくれた香西監督。上映後、参加していた方に監督自らスタンプしてくれるサービスも!
さぬき映画祭2026ーー映画の“今”に出会う2日間

今回のコメンタリー上映で語られた言葉の数々からも伝わるように、映画はいつの時代も、観る人の人生とともに新しい表情を見せてくれます。
そんな“映画の魅力”と出会える場として、今年も「さぬき映画祭2026」が開催されます。
会期は2026年2月7日(土)・8日(日)。
20周年となる今回は、例年以上に素晴らしいラインナップが揃う特別な年です。
ゲストのお二人も受講したシナリオ講座受講生で、第8回シナリオコンクール大賞を受賞した 松田恒代監督『ワタシ、発酵します!』も公開予定。
“映画祭だからこそ見られる作品”が揃う、見逃せない2日間となりそうです。
映画好きの方はもちろん、これから映画を深く味わいたいという方にもぴったりの映画祭です。ぜひ会場で、映画が持つ新しい一面に出会ってみてください。
さぬき映画祭ホームページはこちらから!